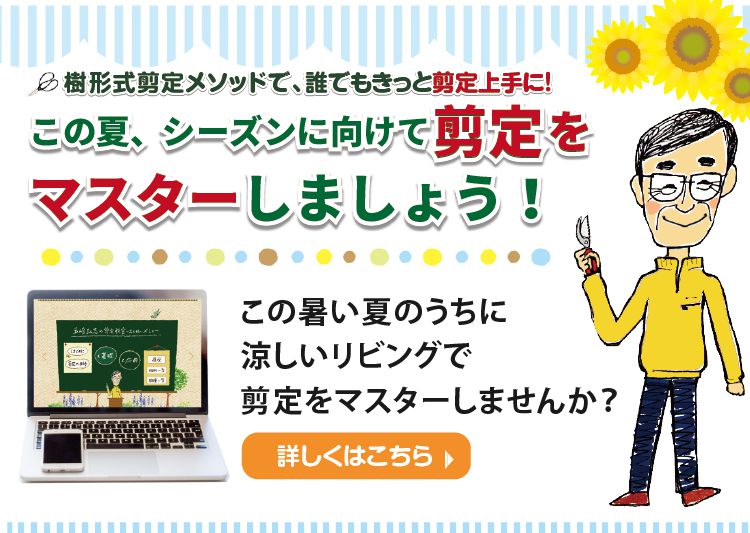こんにちは、庭木の剪定ドットコムです。
先日、インターネットのとあるページでこんな一文を見つけました。
玉作り剪定の解説だったのですが、
と書かれていたのです。
刈り込み剪定の基本を既に知っている方なら、きっと「あれ?」と思ったのではないでしょうか。
そして、この解説通りに刈り込み剪定をした後の残念な様子が、目に浮かんできたのではないでしょうか。
そうです。
上記の解説には大事なポイントが抜けていますね。
間違った剪定方法で大事なお庭をダメにしてしまう前に、玉作りや玉散らしの刈り込み、生垣の刈り込みに共通しているの大事なポイントを、これから補足したいと思います。
もし忘れてしまっている人は、もう一度、刈り込み剪定の基本についておさらいしましょう。
玉作りや玉散らし、生垣の刈り込みに共通する大事なポイント
玉作りや玉散らしの半円形の樹形は、自然界にある形ではありません。人工的につくる形です。大きさをコントロールしながら、あの半円形を維持していきたいものです。
そのためには、まず表面から覗いて見て、太い枝や強い枝は少しハサミを枝の中に入れて、小枝のある位置で切り戻し剪定をしておきます。
こうすることで、その後に勢い良く飛び出す徒長枝の発生を抑える事ができます。
また強い枝が表面近くに無くなるので、半円形に刈り込むときにも刈り込みばさみをスムーズに使うことができます。
【間違った剪定例】


このまま生長していくと、強く勢いの良い枝はどんどん伸びていき、半円形の仕立て樹形がゆがんでいってしまいます。
刈り込み剪定のまとめ
玉作りや玉散らしのような仕立てものや一本立ち、株立ちの樹木、常緑樹、落葉樹、花木も、どれも剪定の基本は同じです。
尚、それぞれに剪定に適した時期(適期)がありますので、確認してから剪定を行ってください。
剪定作業が終わったときが剪定の終わりではありません。
剪定後に伸びた枝がつくる樹形を意識して剪定するように心がけましょう。